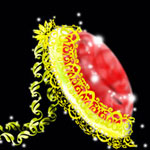
【伯爵夫人の恋人 第七話】
この世の出来事は、すべて綾なす糸の如し・・・。
世の理は、この糸を切っては紡ぎ、紡いでは切り。
けれど、それは断ち切れる事はなく。
延々と続く。
終わりに向かって。
「・・・これは、姫君。」
「様子は。」
「ここ数日微熱が続いております。」
「痛みは。」
「多少なりとあるようですが・・・なにぶん我慢強い性格なので・・・。」
「ふむ・・・。」
「ただ・・・体力的には、もう・・・。」
「そろそろ限界か。」
「はい。」
デイノス城の地下。内離宮と呼ばれる女神の居住空間にある幾つかの部屋には、「神の児」と呼ばれる選ばれし人間が
数人暮らしている。その中でも、女神が「我が子」と呼び大切にしているのがこの年28歳になるトレイアスの愛娘・ライラで
ある。ライラは幼い頃の怪我が元で下半身不随となり車椅子での生活を余儀なくされていた。最近では、ここ数年の無理
な生活が祟ったのか体調不良が続き、ベッドから出られぬ状態にある。
今日は、特に体調が悪い。そんな事を知らせた訳ではないのだが、女神は勝手知ったる何とやらで突然ライラの部屋
を訪れた。何となく訪れたのではない。女神の行動にはすべて意味があるのだ。思った通り、一人の男がライラの傍らに
甲斐甲斐しく付き添っていた。その様子に、女神は苦笑いを噛み殺す。ディオネイルの影武者を務め、冷酷非情を友と
する軍師・ドゥオル・アームス・ジア。愛称・ドール。人形のように整った美貌を持つ典型的な冷血漢・・・の、成れの果て。
彼の過去を知る者ならば、なんとまぁ甘くなって、とでも言いそうだ。惚れた弱みとはよく言ったものよ。
「薬だ。目覚めたら飲ませておけ。」
ドールに代わってベッド脇の椅子に腰を下ろした女神の言葉に、ドールはスッと腰を引いて剣士の礼をとる。元々は大
陸の端にあった小国の貴族だというが、ディオネイルの影武者であっただけに行動は彼そっくりだ。
「は。ありがとうございます。あの・・・。」
言葉の選び方まで似なくていいものを。背に流れる黒髪が小首を傾げる度にサラリと揺れる。そんな様までディオネイ
ルそっくり。尤も、彼の髪は琥珀色だが。
「なんだ。」
「・・・この状態があまり続いては・・・。」
「解っておる。」
「では?」
「治療の準備は整っておるのだ。ただ、今、我は困っている。」
「・・・困って?」
「ライラの代わりを務める者が必要だ。それをやっと手に入れたが、目覚めぬ。困ったものだ。」
言葉とは裏腹に、女神は如何にも愉しそうだ。何処が困っているのだろうか。天才軍師と謳われたドールの切れる頭を
持ってしても、この幼い女神の言動に付いてゆくのは大変である。
「それは・・・伯爵夫人の?」
「ここでは昔の身分など意味はない。」
「失礼しました。」
「何しろやんちゃな「我が愛し児」はライラが大好きだからの。その代役を務められる者などそうそうおらぬ。唯一代役の出
来るアイラは別件で使えぬしな。」
アイラとは、ライラの二つ違いの妹である。トレイアスの子供たちは皆血の繋がりが無い。その中では珍しくライラとアイラ
は実の姉妹である。性格や姿形もよく似ている為、双子と間違われる事が多い。
「目覚めぬ理由は?」
「精神的な傷だ。気が弱すぎる。」
「傷・・・。」
「今の時代、無知な箱入り貴族が生き抜く術など知れている。まして女ならば尚更な。それが息子の精神に傷を残した。
そんな心の空隙に悪夢が入り込んだのだろう。記憶を消す事も考えたが、それでは使いものにならぬ。我が子の身代わ
りとして拾ったが、これでは意味がない。」
つまり、あの子供はライラの身代わりとして「やんちゃ坊主」の世話をする為に拾われたのか・・・。ドールの脳裏を元気
いっぱいの幼子が横切る。母を亡くした幼子は、けれど、母が生きていた頃からライラに懐いていた。ドールからすれば
異常なほどに。
そして、異常な執着を持つのはこの女神も同じ。ディオネイルしかり、やんちゃ坊主しかり。ライラしかり。女神の執着は
時に度を超えている。
「母親に会わせてみては。」
「あの女を我の部屋に入れよ、と?」
「申し訳ありません。」
ドールの言葉に冷たい女神の視線が動く。侮蔑と嫌悪。女神はとことんセアラが嫌いらしい。
「まあよい。いざとなったら強引に目覚めさせよう。それで精神が壊れたら諦めるしかあるまい。母親共々処分して、アイラ
の件を後回しにする。」
「は・・・。」
態々死者を蘇らせておいて、それを再び殺すとは。他に利用しようとは思わないようだ。女神の思考回路は謎だらけで
ある。
それでも、そっとライラの額に触れる女神の指先は限りなく優しい。
何を考えているのだろう。
十以上も年上の女を我が子と呼ぶこの幼い女神は。
「まぁ・・・姫様。」
長い睫毛がフルリと揺れて、琥珀の眼差しが女神の存在を捉える。女神は一種独特の冷気を纏う為、どれほど深い眠
りにあってもライラは目覚めてしまうらしい。尤も、その冷気を感じ取れない人間も多いので、気配のない女神の突然の登
場に心臓を悪くするものもいるらしい。今は東の砦に出向いている友のギョッとした顔を思い出し、ふとドールは口元を綻
ばせる。友は性格が開放的なのでいつも女神の冷気を捉えるのが遅れてしまうのだ。その為、女神に揶揄われる事も多
く、気に入られてもいる。
質素な寝台が軋む音に、女神はそっと白い指先で横たわる躰を制した。琥珀の長い髪が舞う清潔な木綿のシーツは、
この時代にあっては贅沢の極みだろう。真新しく織り上げられたばかりのそれがこの部屋に届けられるのも、女神の寵愛
が深いからこそだ。
「起こしてしまったか。」
この娘に対しては、女神はどこまでも温厚だ。その恐ろしい牙を完璧に隠してしまうほどに。
「いいえ。ドゥオル様・・・姫様が来られたならば、起こしてくださればよかったのに。」
「すまない。」
ライラの掠れた声に、ドールの胸が軋む。元々丈夫な躰ではない。それでも、出会った頃はバラ色の頬をした娘だった
のだ。今、その頬には血の気すら感じられない。
「気遣いは無用だ。気分は。」
「ゆっくり眠らせて頂きましたので。」
「ふむ。あのやんちゃがいてはゆっくり出来ぬか。」
「まぁ、そのような事はございません。元気な声が聞こえなくて寂しいですわ。」
いつもライラの膝で甘えているやんちゃ坊主は、父親と一緒に東の砦に行っている。ライラの体調が思わしくない為、そ
の負担を減らそうと急遽、父親に同行させたのだ。
「そなたには、苦労を掛けるな。」
ぽつりと零れた女神の呟きに、ドゥオルは目を見開き溜息を噛み殺す。世界広しと言えど、女神にここまでの感情を吐
露させるのはディオネイルを除けばライラだけだろう。
女神は元々感情の乏しい存在なのだ。
「姫様。」
「だが、その礼はさせてもらう故に。」
「礼だなどと・・・わたくし共こそ拙きお仕えしか出来ませぬのに。」
「充分ぞ。」
その一言を合図に女神は立ち上がる。無用に長居をしてはライラが気を遣い疲れてしまう。
「ドゥオルに薬を渡してある。飲んだら眠れ。」
「はい。ありがとうございます。」
「ライラ。」
「はい?」
「無理はせずともよい。まずは己の身を愛(いと)え。大事な躰ぞ。」
「・・・はい・・・?」
少し戸惑ったライラの穏やかな微笑みに、女神は唇の端を僅かに持ち上げて頷いた。
あまり時間がない。そう思わせるほどにライラの躰は弱っている。元より自己犠牲の星に生まれおちている娘だ。己が人
の役に立つのなら、その身の負担など考える事はない。
これも、巨星の影響か。皮肉なものである。
女神は視線でドールを扉の外に連れ出すと、胸の前で腕を組み、長身の顔を斜に見上げた。美しい紅玉の瞳が硬質
な輝きに彩られる。女神の瞳は光の加減に関わらず色を変える性質を持つようだ。人とは異質なその存在は、好奇心旺
盛なドールの心を捉えて離さない。
ディオネイルとは別の意味で、ドールもまた、幼いこの女神に魅せられてしまっているのだろう。
「闘技場建設の一件だか。」
会話は、いつも唐突に始まる。
「はい。」
「着手しよう。」
「本当ですか?」
「人足を雇い入れる為の食糧の目途が付いた。」
この地に戻って一年。女神の助力により何とか生活にも少しばかりの余裕が出来た。次は元々戦闘集団である男達の
日常を取り戻さねばならない。それには、どうしても身体を鍛え直す為の闘技場が必要だった。この城内にも幾つか適当
な広さを持つ庭はあるのだが、今は畑として利用されている。筋力などは狭い室内でも鍛えられるが剣術となるとそうはい
かないのだ。
その為、ひと月前からドールが申請を出していた。小さくても良いから闘技場が必要だ、と。
だが、それには相当の人材が必要だ。当然、その人材の為の食糧も。だから、人材は兎も角、食糧事情を考えると当
分は無理だろうとドールは思っていた。まさか許可が下りるとは。
「嬉しいです。我らは元々剣闘士。戦がなくとも身体だけは鍛えておきたいと思っておりましたので。」
しかし、どうやら裏事情があるようだ。女神の視線がそう言っている。
「ドゥオル。」
「は。」
「戦がない?」
「え・・・。」
「本気でそんな事を思っておるのか? そなたらしくもない。」
女神の言葉に、ドールは頭をフル回転させる。言葉の意味。視線の意味。そのすべてを読み取らなくてはならない。
「・・・。」
「戦など、そこここに転がっておる。頭の痛い処だがな。」
女神のこの口調・・・あちらか。
「・・・中央が動きますか・・・こんなに早く。」
中央とは、エザンドーエンの王都。国王軍を指す。
ドールの言葉に女神は意味深な視線を返した。
「砂漠が騒がしい・・・。」
女神の言う砂漠とは、移動国家アマーンの事だろう。彼等は広大な砂漠地帯を移動しながら生活している。建国は古
く、古代より続く女王国家であり、国民の90%は女性という女国(じょこく)でもある。その半面、代々の女王は戦上手として
も知られ、優れた軍事国家だ。
「砂漠・・・アマゾネスですか。オアシス狙いで?」
だが、砂漠の地下水脈は数十年単位で移動すると聞いている。しかも、移動先は砂漠の民にしか解らない。ああ、女神
には解るか。しかし、中央には解るまい。それなのに戦争を仕掛けるというのか? 無謀過ぎる。
因みに、アマゾネスとはアマーン国の女兵のみで編成される国軍の総称だ。
そんなドールの疑問はすべて顔に出てしまっていたらしい。というより、隠す必要がない。何より、女神相手では隠すだ
け無駄だ。
疑問符の飛び交うドールの眼差しに、女神は唇の端だけを持ち上げて笑った。
「否。女共が中央を狙っている。上質なオスが必要なのだ。やつらは。」
なるほど、そういう事か。ならば、とばっちり回避策を練らねば。
「備えよ。」
「御意。」
女神と智将の会話は短い。この調子で世界を激震させるような重要事項が決まってゆくのだ。あっさりと。
「闘技場建設についてはダグが戻り次第円卓に掛ける。」
ダグは現在東の砦に行っているディオネイルの部下だ。ドールの友人であり、やんちゃ坊主の父親でもある。
「承知しました。」
女神は、ドールの漆黒の瞳に見送られライラの部屋を後にすると、時を置かずにトレイアスを召喚した。
続く。