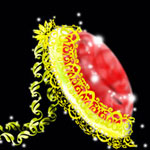
【伯爵夫人の恋人 第六話】
女として下界に残るのなら、人として生きねばならない。
人として、人である男と共に滅びる。それが、本来あるべき姿であり、終焉の美であっただろう。
たった一人の男の為に、少女は迎えの手を振りほどいた。
あの時の胸の痛みを、少女は忘れていない。
けれど。
今、少女は神として下界に存在している。
己の選んだ男と共に、人として、この世界と運命を結ぶつもりであったのに。
滅びゆく世界で、残された刹那の時を穏やかに過ごす。
それが、唯一、少女に残された願いであったのに。
そのはず、なのに。
人として留まった世界で、神として生きる。
なぜ。どうして。
心は堂々巡りを続ける。
後悔している訳ではない。
迷いもない。
ただ、己が神として存在している現実に、やがて男は疲れ果てるだろう。
疲れ果て、ボロボロになって、それでも少女の傍らに存在する事を望むのだろう。
それが、悲しい。
「姫?」
昨夜、広い背中に爪を立てた。
己の背には決して残らぬ痕を、この男の背に残す為に。
「ディル・・・。」
囁くように名を呼べば、心の何所かが幽かに軋む。
求めても、求められても。与えても、与えられても。何処かが餓えて、何処かが貪欲になる。
「私は、貴女の傍にいる・・・何があっても。何をなくしても。」
低く、良く通る声が囁く。
「私には・・。」
貴女だけがすべてだ と。
それは、心地よく少女の胸を満たし。
けれど、その一方で女神の胸を締め付ける。
その言葉を捧げられるべき女は、己ではない。
この男に与えられるべき存在が、きっと、何所かにいたはずなのだ。
「そなた・・・解っているのか・・・。」
「姫?」
「我は、この下界を滅ぼす神と同じ一族なのだぞ。」
「・・・。」
「我が降臨しなければ、こんな事態にはならなかったかもしれぬ・・・そうは、思わぬのか?」
「姫・・・。」
「そなたとて・・・我に出逢わなければ・・・そうすれば・・・。」
「姫・・・私は・・・私は、たとえ時間を戻せたとしても、運命をやり直せたとしても、それでも私は。」
私は、再び貴女と出逢う運命を この運命を選ぶでしょう。
「愚かな・・・。」
「はい。でも、命はひとつですからね。そのたったひとつのものを懸けるなら、やはり私は、貴女がいい。」
人ならば・・・女ならば・・・男の、その真摯な言葉に涙を流すものなのかもしれない。
けれど、少女には、女神には、それが出来ない。
流す涙を、神は持たないから。
だから・・・。
だから、だからせめて、と思うのだ。
せめて、この世界の延命を。
この男の大切なものを護る力を、と。
ただ、望んでしまう。
人としてこの世界に留まりながら、神として生きる。
多くの矛盾を力で捩じ伏せながら。
この崩壊した世界に君臨する。
人と共に有りながら、人とは異なる理の中で。
「私は姫を愛している。だから、何度でも貴女と出逢う運命を選びます。」
「・・・ばか者・・・。」
「ふふ。」
たった一人の男のぬくもりが、少女をこの世界に押し留めた。
それが、人の言う愛であるなどと少女は思わないが、確かに、その男には少女の運命を縛るだけの価値があった。
だが。好きとか、嫌いとか、そんな感情とは程遠い場所に少女の想いはあって、けれど、それを肝心な男は理解してい
ない。心がすれ違っている訳ではないが、他の者達から見れば、その関係はとてもじれったいものだろう。
特に、二人の出逢いから別れ、そして再会のすべてを知る者達にとって、この現状は決して望んでいたものではない。
けれど、二人の犠牲の上に成り立つこの世界では、人の思いだけで変えられる運命などたかがしれている。
もどかしい。
そして、悲しい。
赤紫の空に、黒い太陽が顔をのぞかせる。
淀んだ朝陽。
それでも、人はその瞬間を夜明けと呼んだ・・・。
「なぜ・・・目覚めぬ。」
助けてくれと、生きたいと、望んだのはそなたではなかったか。
「我に救いを求めておきながら・・・その願い、叶えておきながら・・・なぜ目覚めぬ。」
ゆるやかに回転する水の玉。蘇生球を形作る水竜の玲瓏なる深紅の眼差しが、時折、水の壁に現れては少年の過去
を瞳に映す。
血に塗れた両の手。
泣いて縋り付く女。
「我は、応えたぞ。」
その叫びに、その痛みに。
「我は応えた・・・それなのに。何故、目覚めぬのか。」
情事の後の、気だるい時間。
その華奢な躰に毛皮のシーツを巻き付け、女神は独り、その少年と対峙する。
助けて・・・。
誰か助けて・・・。
人間の、その心の叫びが女神に届くのは珍しい。
種は愚か、生命の根源すらも異なる神と人。その精神世界に立ちはだかる壁は想像以上に高く、厚く、強固だ。その壁
をすり抜けて届いた叫びに興を惹かれ、女神の触手が動いたのはこちらにも事情があったからに過ぎない。
どうしても人材が必要だった。
それも、女神に従順で精神の疎通が出来る存在でなければならない事情が。それは類稀なる素質を持った人間でな
ければならず、けれどその存在は決して多くない。
それが、図らずも突然現れた。
女神の精神世界の壁をするりとすり抜けた痛みと悲しみ。母を助けて欲しいと泣く子供。
正直、女の方はどうでもよかった。最初から二人を助ける気など、女神にはなかったのだ。泣き叫ぶ子供が欲しかった。
生きたいと望む少年の思いが。だから、必要とあらば心の傷となる記憶など消してしまえばいいとさえ思っていた。
必要なのは女神と意思を共有出来る存在。ディオネイルの場合は特殊だが、この子供は彼に限りなく近い素質が感じ
取れた。
これは使える。
女神の意思が働いた。女は見捨ててもいい。はっきり言って、女神の最も嫌いなタイプの女だ。泣くしか出来ないという
思い込み。自ら何もせず周囲に流され、傷つけられても仕方ないと諦め、これが息子の為なのだと都合のよい大義名分
で楽に生きる術を無意識に選び取る。箱入り娘といえば聞こえは良いが、ただの無智。そして無知。無恥。あの女に対し
ては辛辣な言葉しか思い浮かばないが、それは仕方ない事だ。
母の強さより、女の愚かさに生きるセアラという名の人間。言い訳だけは一人前で、自らの手は決して汚さない。
嫌いだった。息子の血に塗れた両の手を洗い流す為の水も手に入れられぬくせに、息子の犯した罪を庇う振りをして
自らを守る女。しかも、すべてが無意識下なのだから最低だ。
だが・・・。
「よりによって・・・。」
まさかと思った。
餓死寸前の親子の縁に絡みつく細くしなやかな運命の糸。それは途切れそうに細く、儚く、しかし繊細で複雑で。
やがて女神は気づく。か細いくせに強靭な運命の糸の持ち主に。
トレイアス・ガローン。下界の命運の一端を握る巨星のひとつ。女神は貢の星と呼んでいるが、この男の下界を操る運命
の力は侮れない。計り知れないと言った方が正しいだろうか。
下界には巨星と呼ばれる運命を持つ人間が何人か存在するが、トレイアスはその中でも最大級の力を持つ星の男だ。
現に、彼の息子は女神の愛人として崩壊した世界の最後の柱となっているし、その部下たちにも運命は容赦なく負担を
強いている。更にトレイアスの養子となり娘たち、息子たちと呼ばれている者たちも女神の支配下にあり、トレイアスに連な
る人間は大なり小なりこの壊れた世界の存続に関わっているのだ。
尤も、トレイアス自身の意思には関係なく世界は動いてゆくので問題はないのだが。
それにしても、今回の一件には苦笑を禁じ得ない。
確かに人材は欲しかったが。それも、トレイアスの娘の為に欲した人材ではあるが・・・。
「トレイアスめ・・・何処までも下界の理に絡んで来やる・・・。」
皮肉のたっぷりと込められた呟き。けれど、その唇に浮かぶ微笑みに不快感はない。
トレイアスは、未だ女神が彼に女を与えた本当の意味に気付いていないのだろう。健康な若い女を与えた意味を。
あくまで、女神が欲しいのは子供の方だ。だが、今となってはそれだけで済みそうにない。女神は欲深い生き物らしく、
一石二鳥どころか、三鳥、四鳥を狙っている。
それには、一刻も早く子供に目覚めてもらわなくてはならない。
「可愛い我が子の為に、手段を選んではいられぬな・・・。」
女神の瞳の奥で穏やかに微笑む琥珀の娘。心優しく、脚の悪い美姫。早く治療を始めなくては、女神の計画にも支障
が出て来る。
その為には、何としても子供が、セナスティアが必要なのだ。
トレイアスとセアラの事は、その副産物に過ぎない。
蘇生球はゆるやかに回転を続ける。
その中で眠り続ける子供は悪夢から逃げ続けている。目覚めてしまえば悪夢など意味もないのに、それでも目覚めない
のは現実に疲れ切ってしまったからだろう。
血に塗れた手を洗う事も出来ない現実と、向かい合う勇気は未だ持てない。助けられた現実を子供は知らず、ただ、悪
夢に泣きながら眠り続けている。
眠りの深さは、子供の心の傷の深さでもある。蘇生球を形作る水竜も、子供の心の傷までは癒してくれない。
類稀なる素質も、このままでは価値はなく、遠からずその存在自体に意味を無くしてしまうだろう。
このデイノスでは、女神に価値を認められない者など生きてゆけない。
さて、トレイアスはどうでるかな・・・。
女神の唇に浮かぶ微笑みは深くなる。
下界の暮らしは退屈しなくていい。
続く。