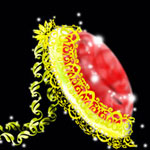
【伯爵夫人の恋人 第九話】
水の無い世界など、きっと人は想像もした事はないだろう。
この下界では、水は当たり前に存在していた。
砂漠にすら、汲めども尽きぬ地下水脈があり、北の山河には雪と雪解け水が、南の大地には果てのない湖が見せる水
平線が、西には雨期が、東には大国を二分する大河が。下界のすべての生き物を潤すだけの水が、確かに五年前まで
存在していたのだ。
雨が、雪が、潤す大地。
井戸の底には絶える事無き水面。
壮大な山並みの麓には湧水が溢れ川となる。
干ばつや猛暑は度々あれど、水そのものが失われるなど人は考えた事もなかった。
それほどに、この世界には水が溢れていたのだ。
だから、人は知らなかった。
水の無い世界を。
コップ一杯の水で、人の命が買えてしまうなど。
一滴(ひとしずく)の水を奪い合い、殺し合う現実など。
たかが水。
されど、命の源。
たかが水。
されど、世界のすべて。
この世界そのものが、水の女神によって造られた事を。
人は。
長く、永く忘れていたのだ。
「人というのは不思議な生きモノよ・・・。」
確かな鼓動を刻みながら、目覚める事のない命。
それを眺めながら、少女はぽつりと呟きを落とし、真新しい布で華奢な躰を器用に包み込む。
水の女神たる少女が身に纏うのは、清潔な白い一枚布。ドレスに仕立てては、という周囲の意見には耳も貸さず、少女
は柔らかな肌を一枚の布だけで覆ってゆく。
布は、とても貴重だ。蚕にしても真綿にしても育てる為には水がいるのだ。例え布自体が手に入っても、今、この世界に
は洗濯をする為の水がない。無論、このデイノスは例外だが。それでも、布をドレスに仕立ててしまえば、次に使えなくな
る。一枚布ならば子供の服が二着作れるが、ドレスからは一着しか作れない。端切れにも色々使い道はあるが、貴重な
布を無駄にしない為には刃物を入れない方が良いに決まっている。
それを、少女はよく解っているのだ。
そういう部分では、この幼い女神は人よりも人らしいとディオネイルは思う。否。貴族よりは人らしい、と言うべきか。
あの日。神々の逆鱗に触れ、その報復が始まった時も、その後も。貴族という生き物は、他の命を犠牲にしてもその生
活を変えようとはしなかった。
結果が、今の、この有様だ。
「姫・・・キツクはありませんか?」
物思いに耽る少女の前に膝をつき、ディオネイルはその細い腰に馬革の帯を巻き付ける。白と栗毛。たったそれだけの
装い。それでも、この少女の美貌が損なわれる事はない。
「ディル。」
「・・・はい。」
「血など、人を形作る膨大な情報を持っただけの、ただの液体に過ぎぬ。情など、姿形無き記憶の連鎖反応だ。意識と
精神は貯蔵された記憶より生まれ、その連鎖反応の結果が喜怒哀楽という感情となる。それだけだ。」
それなのに・・・。
「親子の情、とは、なんだ?」
「え?」
紅玉の視線の先で眠り続ける子供。
ゆるやかに回転を続ける暖かな蘇生球は、母たる命の揺り籠となって子供を護り続けている。
だが、それにもやがて終りの時は来る。
「個たる存在でありながら、なぜ、これほどに影響し合うのか。理解出来ぬ。母親の心の傷が、子の目覚めを阻むなど。」
「傷・・・ですか。」
「そうだ。今、この時代。生きる為に綺麗事など言ってはおられまい。それを理解していながら、なぜ、こうも穢れに囚われ
るのか。」
「穢れ・・・?」
「うむ。我が降臨した際、城で祝典が行われたろう? あの莫迦騒ぎの時、タチの悪いのに目を付けられたようだ。神々の
報復が始まって、いよいよ生きるか死ぬかの瀬戸際に追い込まれているところを付け込まれたのだろう。僅かな食料と
水。その引き換えに貞操を失った。」
よくある話だ。
何処にでもある。
世界が崩壊する前から、いつも、何処かにあった卑劣な男とか弱い女の物語。
世間知らずの美しい未亡人を見染めた男は、無骨で大人しい田舎貴族。彼にとって未亡人は高嶺の花。決して叶わ
ぬ片思い。
だが、ある時、男は手に入れる。水という名の力を。
力は魔物だ。
無骨で大人しい男を、水という力が豹変させてしまった。
それまで手に入れる事の叶わなかったものを容易く手に入れられる力。男の領地に点在していた、それまで役に立つ
事のなかった湿原。それが、男を狂わせたすべての発端だった。
「特殊な環境にある湿原だったようだ。つい最近まで、僅かながらも水が残っていた形跡がある。もう、涸れてしまったが
な。」
湿原の水には毒が含まれていて、それを濾過出来る方法は代々の領主のみが知っていた。
水を失った世界に、僅かに残された水源。しかも、その水は領主にしか濾過出来ない。
それまで田舎者扱いされ、常に嘲笑の的となっていた男。
その立場が、水という力によって逆転する。
彼は、狂った。
湿原の水も永遠ではない。ならば、今を欲望のままに生きよう、と。
「それでは・・・。」
「祝典の際に見染めた女を手に入れるのは簡単だった。」
世間知らずの姫君。物の価値など殆ど知らない。
深刻化する水不足に、夫と両親が残してくれた莫大な遺産もすぐに使い果たした。必死で夫の残した薬草の庭を守ろ
うとしたのだ。
だが、結果は。
タチの悪い男に貞操を奪われ、誇りはズタズタ。
その上・・・。
「真実を知った子供に必死で手に入れた命の糧を拒絶され、結果、共に王都へ逃げたようだが。タチの悪い男の餌食と
なったのは一人や二人ではなかったろうからな。王城にも妾がいたのだろう。結局見つかって、子供は母親を救おうと男
を刺し殺した。」
「それ・・・は・・・。」
「なんだ。」
あっさりと言ってくれる・・・。
元より神たる少女には人間の感情が理解出来ないのだろうが、それにしても。
「姫・・・心の傷が癒えるのには、とても時間が掛るのです。特に子供は。私の時もそうでした。」
身重の母が目の前で殺された時。あの心の傷。今もなお、精神の何所かで燻り続ける痛み。
まして、母親が自分の為に身を売るような真似までしていたとなればショックは大きい。しかも、それを救う為に自らの手
を血で汚したのだとしたら、子供の心の傷はどれほど深いのか。
だから、母親は会おうとしないのか・・・。
穢れた自分の存在が、これ以上息子を傷つけないように。
「そんなものか?」
「あ・・・。」
意味深な少女の視線。
「ディル。心が無防備だ。悲壮感漂う感情が丸見えだぞ。らしくない。」
あっさりと心を読まれた。否。見られたのか。あくまで少女は無表情だが、その機嫌は最悪だろう。
「すみません・・・。」
「構わぬ。だが、己の中で美談にはするな。我が身を犠牲に子を護る母、などと。そんな綺麗事な話ではない。」
「え・・・。」
「無智は最悪の罪。無知は最大の罪。知恵と知識があれば、少なくとも息子の手を血で汚す事はなかった。行動を起こ
そうと思えば回避出来たはずの悲劇だ。」
「姫。」
「結局、貴族という殻から、城という殻から、己という殻から、出たくなかったのだ。あの女は。」
知ろうとすれば、識(し)ろうとすれば、学ぶ機会などいくらでもあったはずなのに。
どうにもならない。自分は無力だ。誰も守ってくれないのだから仕方ない。
そんな言い訳で、すべての可能性を否定した挙句の悲劇。
それを今更、会わない事で何事も無かった事になど出来るか?
「姫・・・人は、それほど強くありません・・・。」
「解っている。」
「まして夫人は世間より隔離されるように育ちました。」
両親の愛情ゆえに。
夫の盲目的な想いゆえに。
「外を恐れるのは仕方のない事です。」
光り溢れる世界から闇の底に降りるようなものだ。
崩壊した世界の地獄絵図は想像を絶していたのだから。
まして、手の中の宝石のように大切に育てられ、守られて来た女だ。ある意味、自我も自己主張もない。自分の存在そ
のものを依存して生きる事しか出来ないのだ。
「姫には納得出来ないかもしれません。しかし・・・。」
「しかし?」
「弱い者は存在するのです。自分ではどうする事も出来ないほど、生きる事にか弱い人間はいるのですよ。」
その上。追剥、盗賊、殺戮者の群れが昼夜を問わず国中を荒らしまくる中で、身を守るすべもない母息子が王都への
旅をするなど土台無理な話だ。
ある意味。身を犠牲にしても領地の城から出なかった女の判断は正しかったとも言える。王城に行ったからといって、安
全に保護してもらえる保証などなかったのだ。その前に、王都に辿り着けたかどうかさえその当時ならば怪しいものだ。
結果的に王城での保護は叶ったが、結末がこれでは救われない。
世界の何処か、ではなく。
何処かの誰か、でもなく。
世界が崩壊し、誰もが渇き、餓えているのだ。
生きる本能のままに形振り構わず殺し合い、奪い合い、怒り、悲しみ、嘆き。
そんな中で身を寄せ合い、懸命に生きていた母と息子。
母親は子を護りたかった。何を犠牲にしても。その結果悲劇が生まれたのだとしても、それを責める資格が誰にあるとい
うのか。
しかし・・・。
「だから、美談になどするなと言っている。」
少女は、ディオネイルの思いを否定した。
「我が気に入らぬのは、そんな事ではないよ。」
「姫?」
「我が言っているのは、そんな当たり前の事などではない。」
「・・・。」
「我は、言ったはずだ。今の時代を生きる為に、綺麗事など言ってはいられない、と。だから、そんな事を不快に思ってい
る訳ではない。」
「では。」
「ディル。我は『雌犬』など好かぬ。」
ああ。
紅玉の瞳に浮かぶ嫌悪と侮蔑の意味が、やっと解った・・・。
『雌(おんな)』になってしまったのだ。夫人は。
自分を犯す男を嫌悪しながらも、夫人の躰はその意思に逆らった。
しかし、それは・・・。
「姫・・・。」
多分。どれほど言葉を重ねても、この美しい少女には理解出来ないだろう。
時に人の肉体は心を裏切り、心は肉体と切り離せない処にありながら、決してひとつには成り得ない。
どれほど心が男を嫌悪しても、肉体は快楽を貪り蕩けてゆく。抗おうとして抗い切れるものではない。
快楽は、人にとって必要なものなのだ。
「そろそろトレイアスが来る・・・。」
「姫、お待ちください。」
「ディル。」
「は・・・。」
今日の謁見の場に同席する事は許さぬ 。
続く。