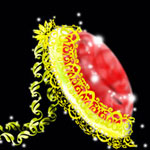
【伯爵夫人の恋人 第五話】
漆黒の闇という名のたゆたう水の底。
ゆらりゆらめく意識の下で、ふと、誰かの泣き声がする。
また、そなたなのか・・・。
女神のその呟きは、今は決して言葉にならない。
たゆたう意識が目覚めを拒む。
久方ぶりの逢瀬に深く眠る男は酷く鋭敏で、腕の中の存在が幽かに身じろぐだけで目覚めてしまう。
なにより、男と過ごすこの時間は貴重だ。
背に規則正しい鼓動が聞こえる。
すっぽりと背後から抱き締められて、華奢な躰は熱い肌に溶けてしまいそうだ。
心地がいい。気持ちがいい。下界に降臨して初めて知ったぬくもりがこの男の肌だった。
だから、この地に留まっている。
この崩壊した世界に。
「ディル・・・。」
囁くようにその名を呼べば、男の覚醒は驚くほど速い。
その目覚めと共に、躰に深く穿たれた楔も熱を帯びる。
この瞬間の、ゆるやかな腰の蠢きが殊の外気持ちよくて、蕩けるように熱い吐息が無意識に零れ落ちてしまう。
「ん・・・姫・・・?」
相変わらずひやりと冷たい柔肌を抱く腕に軽く力を込めながら、意思をもってディオネイルは腰を蠢かす。冷たい肌にも
関わらず、その胎内(ナカ)は驚くほど熱く、呑み込んだ楔を締め上げて来る。
「ひ・・・めっ。」
「あ・・・っ・・・。」
この瞬間はディオネイルにとっても堪らなく心地よい時間だ。ゆらゆらと腰を揺らしながら、汗ばむ掌を柔らかな下腹部
に押し当てる。
決して実らぬ種だと解っていても、この掌に感じる震えだけは現実のものだと確かめたい。
「くっ・・・。」
腰の動きが確実に果てへと向かう。掌の下で、その熱が激しく弾む。細い腰。薄い皮膚。骨ばった手の甲に小さな爪が
痕を刻む。
離さない。
たとえこの行為が神への冒涜だとしても。大罪だと解っていても。この腕の中の存在だけは、決して失う事など出来な
い。
「イ・・・くっ。」
「はぅっ。あ・・・っ。」
目覚めの後の、この開放感が堪らない。
ふるふると震える快感の残像。華奢な躰がすべてを受け止め快楽に蕩けてゆく刹那の刻。
「ディル・・・。」
「そんな顔をすると、またベッドから出られなくしますよ?」
普通の恋人たちのように愛し合う。
許し、赦され、求め、与えられ。
「有言実行だからな。そなたは怖い。」
「ふふ。姫には敵いませんが?」
「戯け・・・。」
けれど 。
けれど、震える胎内に解き放たれたこの想いは、一体、何を生み出してくれるのだろう。
「それで・・・そろそろ教えて頂けませんか?」
「ん?」
「父の一件です。なぜ、セアラ夫人を父に?」
「・・・。」
「貴女の事です。ついで、という訳ではないでしょう。元々父とセアラ夫人には面識がある。尤も、あの状態では父にも最
初は解らなかったようですが・・・態々父に行かせた時点で、貴女にはすべてが解っていたのでは?」
「ふふ。」
「ミイラの如き二人を救い、死したる子を蘇生させてまで手元に置きたがる理由。私が聞いてはいけない事ですか?」
「いや。」
「では、なぜ?」
死者を蘇らせる・・・言葉にすれば簡単な事だが、実際にそれを成し得る事は神といえど本来ならば不可能だ。否、不
可能というよりは、犯してはならない大罪のひとつと言った方がよい。下界には下界の理がある。下界において死はすべ
ての命に対して平等に与えられている唯一のものであり、それ故にこの世界にとって最大の影響力を持っているのだ。
ある意味、神だからこそ、下界において不変の理である死の領域に勝手な事情で踏み込んではならない。
その領域に、この幼き女神はすでに二度も踏み込んでいる。それが、否応なくディオネイルの不安を掻き立てるのだ。
「世界は、滅びてゆく・・・。」
「姫・・・。」
「それは、我にも止められぬ現実だ。」
「・・・。」
「だが、延命は出来る。」
「延命・・・。」
「世界とは生き物だ。大地が生きているように、世界そのものも生きている。人は、それを忘れがちだがな。」
「・・・。」
「延命と一言で言っても、それは人の病を治し、その命を長らえる事とは訳が違う。そなたら人の望みは奇跡を待ち望む
に等しいものだ。神に背き、その逆鱗に触れたそなた等には本来有りえぬ生存の未来。簡単に手に入るものではない。」
「・・・はい。」
「だがな。奇跡は起こすべく準備をすれば、必然として起こるものでもある。」
「準備・・・ですか。」
「そうだ。不可能を可能にする為に。有りえぬ未来を手に入れる為に。緻密で。繊細で。大胆で。そして傲慢な準備が必
要なのだ。」
「傲慢な・・・準備。」
「ふふ。死者蘇生を行った時点で、それは傲慢以外の何ものでもないだろう。死は、この世界の理が、運命という名の自
らの意思で定めたものだ。その運命を勝手に書き換えた。我が神である。その理由だけで、だ。」
さぞ、天上の神々は腸が煮えくり返っているだろう。
人間の存在によって汚れた世界を一度崩壊させ、人間を絶滅させた後、新たな世界を創り出す予定だったものを。そ
の新たなる未来を、新世界の礎となるべき女神が拒絶したのだ。
すべての運命を定めていた神々にとっては信じられない展開だろう。
「ディル・・・この世界の存続は、あってはならぬ未来なのだ。」
神の定めた運命の前に、人は、あまりにも無知で無力だった。
そもそも、すべての考えが甘かったと言っていい。
降臨した女神があまりに幼かったから。
だから、人は勘違いしてしまった。
その幼い姿に。
その稚い声音に。
その天上の美貌に。
タダ、美シイダケノ子供ニ、何ガ出来ルノカ と。
欲しい物は与えてやろう。
我儘はきいてやろう。
ご機嫌取りは人間の得意分野。
支配される事には慣れている。
けれど、相手は子供だ。
お気に入りの青年元帥を傍に置き、その部下を可愛がり、気まぐれに外の世界を見、毎日を気ままに生きる。
存在は異質。
だが、その姿は幼く、愛らしく、人畜無害 それは、本当に?
甘かった。
何もかも。
人間は、最初から対処を間違えてしまったのだ。
女神の、その外見故に。
「姫・・・。」
「なんだ。」
「また誤魔化しましたね?」
「なんの事だ。」
「私の問いに対する答えは未だ聞けていませんよ?」
「ふふ。なぜトレイアスにセアラを・・・か?」
「はい。」
「この世界には、活性薬が必要なのでな・・・。無論、延命治療の為の劇薬も必要だが。何れも手に入れるには時間と準
備が必要だ。」
「活性薬・・・?」
「そうだ。そなたには以前にも話した事があると思うが。トレイアスという男はな、我が降臨する遥か以前から大きな意思の
元に生きているのだよ。それは本人の意思に関わりなく、世界に動かされているようなものでな。それ故に、あやつの存在
に我は大きな期待をしているのだ。」
「この世界が、父を?」
「そうだ。だが、崩壊を始めたこの世界には、あやつの存在意味を生かし切るだけの余力がない。本来ならば、覇王と呼
ばれるに相応しい男だ。その星の下に生まれているのだよ。トレイアスには、我が手を懸けるだけの価値がある。」
そして、お前もまた・・・。
「・・・。」
「姫?」
「ああ・・・。セアラの事は、本当に偶然の重なりだった。偶然が重なって必然になったのだ。我が望んでいたのは息子の
方であったが、下界の縁とは不思議なもの。そろそろトレイアスにも褒美が必要だろうと思っていた矢先、あの親子が現れ
たのだ。」
「褒美、ですか。」
「そうだ。不満か?」
「いえ・・・しかし、褒美が女とは・・・。」
「必然だよ。ディル。」
本当なら、お前にこそ必要であったのに・・・。
「トレイアスには、あまり無理をさせたくない。だが、遊べる女は東の砦にしかおらぬ。我は、秩序が乱れるのを好まぬから
な。色事での騒ぎなど、この城で起こされては堪らん。」
「つまり、父の歳を考えたら近くに女がいた方がいい、と。父が激怒しそうですね。」
「ふふ。そうだな。セアラという女は、それ以外で役に立たぬ。」
「酷いな。」
「そうか。だが、事実だ。我には役に立たぬ人間を養ってやる必要はないからな。セアラがその運命を拒絶するなら、残さ
れた運命は死か、娼婦に落ちるか、だ。トレイアスの性奴として使えぬなら、東の娼館に移す。これは決定事項だ。」
すべての運命は綾なす糸だ。
縦に、横に、それは確実に織り上げられてゆく。
そして、必要のない糸が切られるのもまた、ひとつの運命に過ぎぬ。
この世界の運命の糸が、突然、神の手によって切られてしまったように。
世界は滅びる。
どれほど奇跡を望んでも、人に、未来はない。
それでも、我はこの世界に残ってしまった。
それは、なぜなのだろう 。
続く。