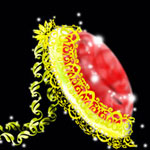【伯爵夫人の恋人 第二話】
かつて『デイノス──死の大地──』と呼ばれた荒野に楽園がある。
そんな噂が実しやかに流れたのは、王都炎上から五年が過ぎた頃だ。
デイノスは、このエザンドーエン王国が軍事大国と呼ばれ、世界最強の名を恣にしていた時代、一人の男が手に入れ
た西の領地であった。
命の育たぬ荒野。
死の大地。
数百年に渡り誰も住んだ事のないこの地を男が欲した時、誰もが首を傾げたものである。
『死の大地に、なぜ我らが勝利の神である大元帥閣下が固執するのか・・・と。』
その理由は、結局誰にも解らない。
元帥の思いが理解される前に、国は、世界は、崩壊したのだ。
神の意志によって。
王都炎上から五年。
まさか、死の大地と呼ばれた辺境の領地が楽園と呼ばれる事になろうとは、誰が想像しただろう。
だが、確かにそこは楽園だった。
なぜなら、水のない世界にあって、唯一、水の溢れる大地だったからだ。
エザンドーエン王国・西の領地デイノス。
壮大なる石の建築物と巨木壁に囲まれた戦士の街。
たわわなる果実、風にそよぐ緑、子供たちの歌声響く大地。
そこは、かつて血の336騎と呼ばれた厳つい剣闘士たちに護られる奇跡の楽園だった。
「セアラ・ヴァジュ・クウォン伯爵夫人・・・。」
「トレアイス様・・・まさか、貴方様でございましたか・・・。」
砂埃舞う荒野でトレイアスが拾った女は、ひと月ほど意識が朦朧としたまま手当を受け、目覚めても口が利けるようにな
るまで更にひと月掛かり、やっとその名を聞き出せたのは保護されて三カ月が過ぎた頃だった。本当ならばもっと早くに
その名を聞き出せたはずであったが、セアラに付けていた使用人は読み書きが出来なかったし、トレイアス本人は暫く邸
を留守にしていたせいもあり、拾った女と会う機会がなかったのだ。
その上、女は世話をしてくれる使用人から「女神は大の貴族嫌い。」と聞かされた為、迂闊に名を名乗る事が出来ず、
自分を救ってくれた男に会うまでは「リーマ」と偽名を使わざるを得なかった。ちなみにリーマとは「森」という意味だ。
ただ、使用人から息子が女神の元で保護されていると聞き、その点でセアラは胸を撫で下ろしていた。尤も、それだか
らこそ自分の身分はなんとしても隠しておかねばならなかったのも事実だ。
けれどこの日。セアラは自分を救ってくれた男の姿に愕然と眼を見開く事になる。
「トレイアス・・・ガローンさま・・・。」
呆然とするセアラの眼に、大きな体躯を小さな椅子に預けた男の姿があった。まだベッドから起き上がる事も出来ない
セアラは眠っている事が多いのだ。
一方、丁度この日、仕事を終えて東の砦から戻ったトレイアスは、意識が戻ったという女の元を訪れ、その寝顔に驚愕し
たまま椅子に座りこんだ。まさか自分の知った女とは思わなかったのだ。
無論、それは仕方のない事ではある。何しろ、拾った時はミイラの如き有様だった女の顔を識別する事など出来なかっ
たし、貴族嫌いの女神が、まさか自分の住まう砦にそんな人間を受け入れるはずもない。
最初からトレイアスの頭に「身分ある女を拾わされる」などという事態は想定されていなかったのだ。だが、目覚めた女が
自分の名を呼んだ時、その想定外の出来事が起こってしまった現実を知った。
「では、あの坊主は・・・。」
「セナ・・・わたくしの息子。セナスティアでございます。」
セアラの言葉に、トレイアスは「あぁ・・・。」と溜息のような、唸り声のような、複雑な声をあげて頭を抱えた。
セアラとトレイアスは親しいというほどの間柄ではなかったが、互いに知らぬ仲でもなかった。ただ、余りにも変わり果て
たセアラの姿に、トレイアスが彼女に気付かなかったという顛末だ。セアラはセアラで、この三カ月、自分を救ってくれた
男に会う機会がなかったので当然のようにトレイアスだとは知らない。何人か会った使用人はこの邸の主を「だんなさま」と
呼ぶだけであったし、セアラ自身、その名を聞く事もなかった。貴族嫌いな女神の元にいるという息子を案じて、余計な
事は一切口にしなかったからだ。
「でも・・・安心致しました。わたくし達を救ってくださったのがトレイアス様で、よかった。」
「・・・どういう意味かの・・・。」
「女神は貴族を嫌っていると聞きました・・・それで、息子の身を案じていたのでございます。」
その言葉に、トレイアスは実に複雑な顔をした。といっても、彼の顔は髭の中にあると言っても過言ではない。その為、
表情などはよほど彼を知っている人間にしか見分けられはしないのだが。
「あぁ・・・その事か・・・。」
「トレイアス様。息子は、セナは無事でございますか? セナさえ無事であるのなら、わたくしはどうなっても構わないので
す。しかし・・・あの・・・どうして女神の元に・・・。」
セアラの声は、美しいソプラノだ。
その声を聞きながら、トレイアスはひたすら顔を顰める。いっそ逃げ出したいくらいだ。
「あの・・・?」
「あ、ああ。あの坊主なら生きているはずだ。だが、わしも仕事で砦を離れていたのでな・・・まだ会っておらん。」
「わたくしも・・・会えますか?」
女神の元にいるのなら、会えないかもしれない。別々に保護された時点で、自分が貴族である事が女神に知れている
のではないかとセアラは怯えている。
しかし、実際はそれどころではない事態だった。トレイアスにとっては、実に由々しき問題が起こっている。
「取り敢えず、わしが内離宮に行って坊主の状態を見てこよう。奥方を連れて行くかどうかは、それからだ。」
「・・・はい・・・。」
トレイアスは、セアラとの話を簡単に切り上げて部屋を出た。逃げ出したと言った方が正しいかもしれない。勿論、セアラ
にそんな事を悟らせる事はなかったが。
「くっそう・・・あの女っ。」
セアラの部屋の扉から数歩離れると、トレイアスは烈火の如き怒りの形相で廊下を走り出した。何としても確認しなくては
ならない。今の子供の状態と、二人を自分に拾わせた女神の真意を。
深い意味もなく、女神があの二人を救う訳がない。それはトレイアス自身が一番よく解っている事だ。
そして半時後。
トレイアスは見事に撃沈され自分の邸に戻る事となる。
あの日。
餓死寸前の二人を連れ帰ったあの日・・・。
「まぁ、酷い死臭ですこと。だんなさま。」
「仕方あるまい。姫の所望だ。」
「お珍しい。女神様が外の人間を? 何者ですか?」
「解らん。親子のようだが・・・。取り敢えず、こちらは生きているようだ。エレム。今後はお前に任せるゆえ、回復するまでは
面倒をみてくれ。その後は姫の指示に従う。」
「はい。で、そちらの子は。」
「死体は姫に届けるしかあるまいよ。必要ならば蘇生させるだろう。」
「閣下が激怒されますよ?」
「知るか。わしの所為ではない。それより、女の事は頼んだぞ。」
「はい。」
すべては、それで終わるはずだった。
拾った子供を内離宮に届け、助けた女を回復させて女神の指示を待つ。
それで、すべて終わるはずだったのだ・・・。
まさか、二人を拾ってみ月も過ぎてから、その事実を女神に突き付けられる事になろうとは。
迂闊だった・・・。
どうして拾った時に気付かなかったのか。
あの女が態々自分に拾わせた。その事に不審を抱くべきだったのだ。
「くそっ・・・。」
あれは知っている眼だ。
「あの女・・・あの小娘・・・。」
己が仕えている少女が神である、と。その事実を、今更、これほど如実に思い知らされる事になろうとは。
「くそっ。わしとした事が。」
────後悔先に立たず。
こんな陳腐な言葉を、このわしが、この歳になって噛み締める事になるなんて・・・っ。
拾った時、その女はミイラの如く痩せ細っていた。
げっそりとこけた頬、眼は落ち窪み、纏った襤褸の上からでも骨がくっきりと浮かび上がり、乾き切った肌は多少の切り
傷程度では血すら滲んでこない。
まさにミイラ寸前。誰の目から見ても助かる確率など限りなく低い。女は、それほどに酷い状態だった。
それでも、その顔立ちが整っていると思ったのは、男が多くの人種と交流を持っていたからだ。痩せ細っていても骨格ま
でが変わる訳ではない。その骨格に多少の肉を付けたところを想像すれば、自ずと顔立ちなど解るものだ。
だが、まさか。
「まさか、セアラだったとは・・・。」
その名を呼ぶだけで、トレイアスの口の中に苦い物が広がってゆく。
「セアラ・ヴァジュ・クウォン・・・。」
結婚する前は、セアラ・ヴァジュ・トーレン伯爵令嬢だったか・・・。
トレイアスは、セアラが彼と出会う前から、セアラを知っている。
正確に言うなら、セアラが生まれた時から、トレイアスは彼女を知っているのだ。
「アーリア・・・運命とは、皮肉なものだの・・・。」
その呟きは、誰にも聞こえない過去からの叫びだろうか。
どれほど後悔しても、過去は変えられない。
時間は決して戻りはしない。
それでも、取り戻したいと願ったものがある。
それは、決して取り戻せるものではなかったが。
だが、今ならば望めるのかもしれない・・・。
女神の支配する、この崩壊した世界でならば。
続く。