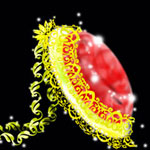【伯爵夫人の恋人 第一話】
連れてゆく・・・。
絶対諦めない・・・。
一緒に行くんだ。
大丈夫、母上は僕が護る。
連れてゆく。
絶対生きるんだ。
今度は僕が・・・母上を・・・。
護るんだ・・・。
連れて行くんだ・・・。
母上を。
女神の住む・・・楽園へ・・・。
神様、女神様、もしも本当にいるのなら、どうか助けて。
僕は子供で、何も力がなくて、何も知らなくて。
それでも、僕は護りたい。
僕を護る為に、僕を生かす為に、僕の為にすべてを犠牲にしてくれた母上を。
神様、女神様。
僕はどんな事でも我慢します。
精いっぱい努力します。
頑張ります。
だから、神様、女神様。
力を貸してください。
僕は、母上を、護りたいんです。
僕は、母上と、生きたい・・・。
ただ、母上と生きたい、それだけなんです。
神様、女神様。
本当にいるのならどうか助けて。
だれか・・・だれか・・・助け・・・て───
吹き荒ぶ乾いた風に頬を撫でられながら、一つの影が荒野にあった。
一つの影は二人の人間であったが、既にその場から動かなくなって随分と経っている。
一人は子供であろうか・・・。
そして、その背にあるのは老婆であろうか。
否。
今、この世界にあっては見た目でその判断をするのは難しい。
まして屍が転がる荒野の真ん中では、遠目でその存在を確認する事すら困難である。
立ち尽くす一つの影が二人の人間である事すら、間近になって解った事だ。
男は、猛禽類の如き鋭い眼を細めると、その有様に大げさな溜め息をひとつ吐き、よく躾けられた愛馬から飛び降りた。
身軽だが、体躯の良い男だ。外見を語るなら筋骨隆々という言葉を具現化したかのような大男で、その猛禽類のような眼
は髭に埋もれるかのように存在し、薄い口唇は男の頑固さと狡猾さ、そして信じる者に対する忠実さが見てとれる。油断
のならない身のこなしと、腰にある大剣だけを見て判断するのなら、騎士か剣闘士あたりであろうか。
大きくて無骨な手が、ふと、顎髭に触れた。琥珀色の視線は、常に目の前の存在から逸らされる事はない。
それにしても・・・。
「生きているのか・・・?」
男の視線の先にある小さな身体が、その痩せた背に長身の身体を背負っている。
否。
最早、背負っているのではあるまい。
小さな身体は既に動く事かなわず、背の身体もまた、凭れたままに動かない。
「少年と・・・女・・・?」
男は片膝をつくと、生きているのかも怪しいであろう小さな顔を覗き込む。
「ほぉ・・・。」
猛禽類の眼に、思わぬ顔立ちが意味もなく映された。
一つの影は、どうやら少年と女・・・女は多分、母親か姉であろう。
身なりは、かつて浮浪者とも乞食とも呼ばれた者共よりも遥かに悲惨だが、今の時代、今の世界にあっては仕方ない。
ただ、この二人はひどく整った顔立ちである。
身に纏う襤褸も、元は極上の絹織物のようだ。
「貴族・・・か。餓えは、極限状態だの。」
動かぬ二人の身体は、見るからに痩せ細り、死神に獲り憑かれている。
だが、生きる事を諦めた訳ではないようだ。共に生きようと懸命に引き摺ったのか、子供の小さな肩には骨ばった細い
腕が食い込み、引き摺られるままにあったらしいその背にある長身の身体の膝下は傷だらけである。
「ふむ・・・女神の気まぐれか。コレを拾って来いなどと。」
男は、呆れたように呟きながらぐるりと首を回し、ふっ、と焼け焦げた空を見上げる。
赤紫の空に、黒い太陽。
夜になると、空は赤黒く変色し、星も月も顔を出す事はない。
神々の呪いにより、水を失った世界。
乾いた大地は悲鳴を上げる余裕もなく、ただ、罅割れてゆくに任せるのみだ。
息苦しい風景に、ふと、男は襟元を緩めた。
「最後に青空を見たのは、何処の地であったかの・・・。」
最後に雨が降るを見たのは、黄金の稲穂を見たは、流るる川に遊んだは、一体いつであったのか。
「もう・・・戻らぬに・・・なぜ、わしは生きておるのか。」
皺の増えた無骨で大きな手。
それを切なげに見つめると、男は過去に思いを馳せる。
かつて男は、数千の部下を引き連れて世界を旅する大商人であった。その生活は絢爛豪華。大国の王侯貴族ですら
も敵わぬ栄華を極めた一族の長として男は長い時を生きていた。
豪快な人生。豪傑の名を恣に、己の信じる道をただひたすら走り続けていた。走り続ける事こそが、男にとって生きて
いる証であったから。
愉しかった。自由だった。世界の広さを肌で感じながら、血生臭い夜を幾度も越え、再び朝陽を浴びられる好運に感謝
して、また、前に進む。
美味い酒と、艶滴る女と、気の置けぬ友と、この手で育てた血の繋がらぬ多くの子供たち。
何処で野たれ死のうとも後悔はない。
そんな人生が、ある日、突然、壊れた・・・。
たった一人の人間の犯した罪によって。
「マントルの悲劇・・・神の力を侮った人間への報復にしては、少々遣り過ぎではないかの。姫。」
呟きは、か弱き人間を嘲笑う乾いた風に撫で梳かれ、意味をなくして砂埃に食われる。
今、男が立ち尽くす大地とて、元は大河の水底だ。大の男を丸飲みするような大蛇が群れて暮らしていた河なのだ。
それが、たった一人の男の罪ゆえに、神の呪いを受け僅か五年でこの有様。
男はやれやれと首を横に振ると、子供を肩に担ぎ上げ、女を小脇に抱えた。
二人の身体は枯れ木のように軽く、乾いた重さしかない。
妙な臭いは、どちらの死臭だろうか。命じられるまま拾ったはいいが、届けモノが死体とは息子に何を言われるやら。
「ん?」
イキナサイ・・・。
ふと、腕に抱えた女が呟いた。
『行きなさい』なのか、それとも『生きなさい』なのか。
尤も、『行った』ところで『生きられる』世界は既に存在しない。死んでいるのだ。この世界は。
「母親・・・か・・・。」
恐らく、そうなのだろう。
死に逝く者の最後の足掻き。
そして祈り。
こういう強さは母性独特のものである。
どちらにしても、まだ女の息はあるようだ。
では、肝心の子供、は・・・。
「必要なら・・・生き返らせるだろうな・・・。」
そういう女だ・・・あの女神は。
人ノ情ナド、理解スルニ値シナイ。
人ノ命ニナド、価値ハナイ。
褪めた口調が言い捨てる現実。
価値ある命には生を。
それ以外には死を。
男の主である美しき女神は、人の情を理解しようとしない。
「それでも・・・わしを今も生かしているのはなぜなのかの・・・。」
思わず愚痴が口を吐いた途端、肩に軽いはずの重みがズシリと来た。子供の肺が動いたようだ。
まだ、助かる可能性はある。
「早く連れて行けとでも?」
物言わぬ子供に皮肉をひとつ。馬の鞍に女の身体を放り上げると、肩に子供を担いだまま男は馬に跨った。
やれやれと手綱を引いた男の身体から、ふわり、と花の香りが漂う。
今、この世界に花は咲かない。
ただ一か所を除いては・・・。
続く。